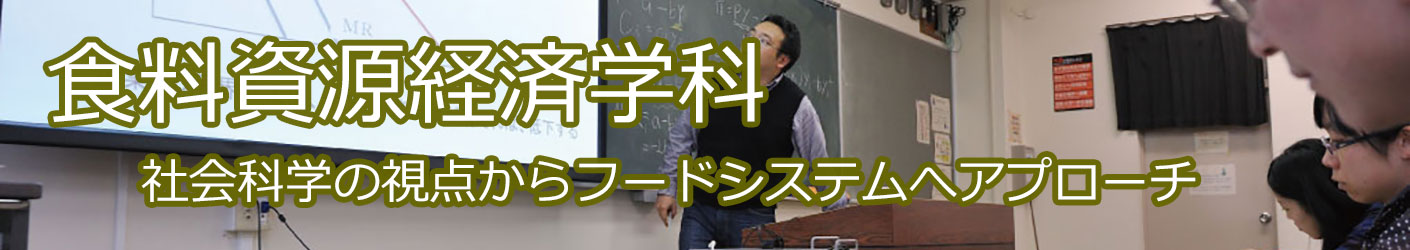
概要

この学科には資源環境経済学とフードシステム学の二つの専門分野があり、自然科学的基礎知識をもとに、園芸に関連した経済学や経営学などの社会科学を習得します。そして「食と緑」に関する社会的要請に応えるため、国際競争力を持つ園芸経営、安全性の高いフードシステムの設計、食品産業の多様な発展、農村資源の有効活用について学び、食料生産や環境・国際協力などの領域の諸問題に適切に対処できる専門職業人を育成しています。
食料資源経済学科教員は積極的に学生の就職支援を行います。多くの卒業生が食品産業、農水省、地方自治体、JAなどの農業団体、国際協力機構等の様々な分野で活躍しています。
フードシステム学分野

食品産業と農業の現状と課題を的確に分析するために、自然科学の基礎をふまえつつ、社会科学(経済学・経営学など)の理論とそれに基づいた分析手法と専門的知識を習得します。 農業生産から消費に至るまで、フードシステム全体を見渡すことのできる幅広い視野を備えるとともに、生産・流通・消費のうち、特定の領域に焦点をあてた専門知識を身につけた人材を育成していきます。

目標
社会科学の視点から、生産・流通・消費に至るフードシステム全体を評価できる人材を養成します。また、食と農に関わる個人および組織の行動様式を学ぶことで、企業・団体の経営戦略や組織運営方策を立案する能力を習得します。さらに、食品安全性の確保に必要な分析視点と専門知識を身につけた人材の養成も目指します。社会の要請に応えていくために
食料経済に占める食品産業(製造業・流通業・外食産業など)の位置づけが高まり、農業生産のみを対象とした分析では、食料に関する問題を部分的・断片的にしか把握できなくなっています。現在、農業から食品産業、さらに消費に至るまで視野を広げたうえで問題点を理解し、その解決策を提案できる能力が強く求められています。加えて、食品の流通システムの変化に伴い、農業部門も食品産業もより主体的にマーケティング戦略を立案する必要があります。取引相手と連携しながら適切に流通経路を管理すること、さらには食品安全性の確保に必要な知識と経営管理能力を備えた人材の養成・配置が求められています。資源環境経済学分野

現代社会が直面している農村資源管理・環境保全・持続的経済開発に関わる問題について、解決への道を自然科学的な素養を踏まえつつ社会科学的に考究し、様々な実践的課題に対して能動的に取り組める能力の習得を目的とします。これらの分野に深い関心を持ち、対象を分析・評価し論理的に表現する能力の習得を目指します。
